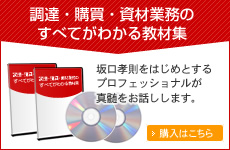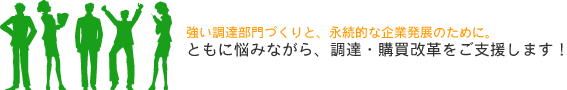昔、ある会社で勤めていたころ、私の昼休みの娯楽は、ひとりで何もない空間を散歩することだった。会社横では、田舎にふさわしく、ただただ畑が無秩序に広がっていた。広大に存在する空、そこにひとり佇む自分。風の音が聞こえてくる。感傷だけがざわざわと音を立てる。会社の横にある小道を抜けて、ぐるりと40分の旅。その景色に変化を見つけることは難しかった。そのとき突然、あまりにも何もない空の下で、絶望感にとらわれてしまったことが何度もある。私は、そこで歩きながらずっと「このままでいいのか」と思いつめていた。私が従業していた仕事に、大きな不満があったわけではない。むしろ、仕事は順調で、やれることの範囲が拡大さえしていた。ただ、それでもなお残滓が私の心を支配し続けた。この空の下には、いまの自分と比べようもないほど成功している人がいる。夢を実現させ、世界規模の活躍をなしている人がいる。たまに読んでいた成功者たちの自慢譚から見たときの自分の姿。もっと違うことができるんじゃないか、もっとやりたいことを実現できるんじゃないか、もっと違う「じぶん」があるんじゃないか。こんなことよりも、他にやるべきことがあるんじゃないか――。いまでは偉そうに若手に指導することもある私の過去は、そんな情けない現実否定に色塗られていた。その後、一般的に成功者と呼ばれる人たちと出会うと、それぞれが深い悩みや葛藤と対峙していることがわかった。それにもう「ほんとうの自分がどこかにある」などという幻想は捨ててしまった。いまの自分しか、ほんとうの自分などない。そう言い捨てる。私のかつての感情を、よくある若者の自己肥大感情として切り捨てるのはたやすい。そして、それは当たっているのだろう。いまでは、私も「豊かになった社会では、<ほんとうの自分>なんてものを考える余裕が出てきたんでしょう」とシニカルに語る。ただ、かつての私と同じように自分探しにさまよっている若手と対面すると、正面切った批判はどうもできなくなる。こんなことよりも、他にやるべきことがあるんじゃないか――。それをいまではまったく私が思わないかというと、それは嘘になるからだ。* * *あるとき、職場の同僚が退職を決めたことを教えてくれたことがある。「ちょっとアジアあたりを旅行して、そのあと、なんかの仕事を見つけるよ。いまの仕事が、やりたいことではないと思ってね」と彼は軽く語ってくれた。「300万円くらい貯金があるからねえ。たぶん1年間は楽勝、もしかすると、2年くらいは生活できるかもしれない」。私は異常なほど彼のことが羨ましくなった。素直に自分の感情を表現できない私がいた。人間が何かを批判するとき、それは自分の正直な感情の裏返しのときが多い。私は「そんなこといっても、日本に戻ってきたときに仕事ないんじゃないの?」「たったの300万円では難しいと思うなあ。それに、貯金を使い果たしてしまうわけでしょう?」「直感では、そんなことやめて資格試験の勉強でもしたほうがマシだと思うけどなあ」。それらのコメントは、すべて自分に嘘をついたものだった。私は言いたかったのだ。「ほんとうにうらやましい」と。彼の仕事はエンジニアだった。日々、市場からの要求を仕様書なる摩訶不思議なものに置き換える。市場の声を聞き、そのワガママで形のない「何か」を具現化しようと奔走する。私の理解できる範囲をこえたアプリケーションを使いこなし、各国の法規に目を光らせつつ、そして安価で、少しでも軽い製品を作るために、終わりのない高度な戦いを挑んでいた。彼は、あれほどまでに複雑な業務をこなしながら、「何のために生きているか」と、まだ人生の意味という単純な問いを考え続けていた。単純な生の衝動に突き動かされていたのだ。私の負けは決まっていた。「ねえ、会社辞めるのって大変じゃないかな」。いつの間にか、私は逆に質問を繰り出していた。「どうやって決断したの?」「何がきっかけだったの?」。彼の体から、ひどく希望にあふれたものを私は感じさせられた。私は彼の眼に洗脳されることを望んでいた。きっとそこには、この瞬間だけでも私を操ってくれる刹那が発見されるはずであった。 * * *職場を飛び出して旅立った同僚について述べた。そこからだいぶ経って、私は彼と同じく職場を去り、違う形で自分の道を歩みだした。しかし、とはいえ、何の迷いもないかといえば、嘘になる。とらえようのない不安と漠然とした恐怖がいつもある。会社という安定した立場にいるときの不満はない。ただし、不安が私を襲い続ける。何かを見ても、考えても、じっとしていられない。そんなとき、ふっと何かにすがりたくなる。そんなときに気を紛らわす酒ばかりはかつてより強くなったけれど、それだって、体を蝕むだけだろう。私が社会人になってから何度目かの夏休み。旅行で来ていた、タイのカオサンロード。バックパッカーたちの聖地として知られるこの道沿いの屋台で、だいぶ前に、彼と同じように職場を捨てた30歳過ぎの「自分探し」男性に会ったことがある。なぜか同席することになった私は、チャンビールを傾けながら、泥酔の果てにその男性に「あてもない旅を続けて寂しくないですか」と訊いてみたことがある。「寂しくなることがある」とその男性は答えた。陰鬱な空気が漂っていた。そりゃ、不安になるよ、と男性は教えてくれた。肩を震わせながら。そして、ただただ飲むことが、その不安を紛らわせてくれるかのように。いまのところに居続けるか、あるいは飛び出すか。そのどちらを選択したとしても、人間に苦悩というものはつきものらしい。丸テーブルでビールの空き瓶だけが転がっているなか、男性は激情を抑え、水産会社に勤めていたこと、あるとき会社が突然イヤになったこと、結婚前に何か自分の可能性を試してみたくなったこと、海外をぶらつきそのなかで自分を見つめ直してみたくなったこと、意外に世界じゅうには適当に生きている人たちが多いと知ったこと、大いなる可能性が広がっていることを知ったこと、そして、なのになぜか寂しくて不安でたまらないこと、を教えてくれた。帰って、これまでのようにサラリーマンを続けてみたいですか、前に戻って同じ職場でやり直してみたいですか、と私が聞くと、その男性は突然、泣きはじめた。静かに、目を強く瞑って、皺をこれでもかと寄せながら、すすり泣いた。私はどうしてよいものかわからずに、混乱して質問したことを後悔し、「すみません」といった。店員は何もわからず、次のチャンビールを運び、テーブルの端に置いた。その涙は、ビール瓶の側面についた結露でびしょびしょになったテーブルの水滴に交わり、同化し、それに逸れた涙は乾いた道路に落ち続けた。(おわり。感傷的すぎました。ごめんなさい) ぜひ、ついでにこちらも見てください!クリックして下さい。(→)無料で役立つ調達・購買教材を提供していますのでご覧ください